東アジアE−1選手権で、森保一監督が率いる日本代表はJリーグの選手で韓国を1−0と下し、3連勝で大会優勝を飾ったが、どこか既視感がある光景だった。
前半、相馬勇紀のクロスをジャーメイン良がうまくマークを外して受け、左足で蹴り込んで先制に成功している。ふたりは大会のベストプレーヤーだった。しかし、チーム全体は徐々にペースを失う。後半は45分間、全員が自陣に引いてゴールを死守。体を張って跳ね返し、セカンドボールを拾うこともままならず、波状攻撃を耐え抜いて、勝利をつかみ取った。選手の健闘には拍手を送るべきだが......。
カタールワールドカップの森保ジャパンは、ドイツ、スペインを相手に徹底した受け身のサッカーだった。圧倒的な劣勢のなか、一発、二発とゴールを決め、いずれも1−2と金星を挙げた。勝利という結果で高評価を受けたが、能動的、主体的な姿勢を欠いたことで格下のコスタリカには敗れ、ラウンド16ではクロアチアに勝ちきることができなかった。
韓国戦は、よくも悪くも森保監督のカラーがチームに投影されていた。受け身で、相手のストロングを消し、逃げきる。その性質が伝わっているのか、もしくは、そうしたサッカーに合う選手を選出しているのか。
これぞ森保ジャパンという戦いだった―――。

韓国に勝利してE−1選手権で優勝を飾った日本代表の森保一監督 photo by Fujita Masato
カタールワールドカップのベスト16でクロアチアに敗れ去ったあと、森保監督はひとつの指針を掲げていた。
「ボールを持っている時間を増やす」
それは、受け身サッカーからの脱却宣言だった。
ベスト8以上に勝ち上がるチームは、「いい守備がいい攻撃をつくる」というのをベースに、ポゼッションでリズムをつくったり、押し込んで先手を取って崩したり、攻撃のバリエーションを出すことができている。守り一辺倒になると、選手の健闘と天運を祈るという偶然性にかけざるを得ない。言い換えれば、それがベスト16の壁になっていたのだ。
それから3年近くが経過したが、戦いのキャラクターは変わっていない。むしろ、「石橋を叩いて渡らない」森保監督の傾向は強まっている。アジアレベルではレベルの差がありすぎ、色合いがぼやけていただけだった。











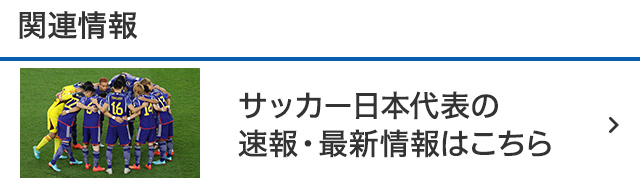







































































![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_108_h_108_q_80/picture/look/s_look-61790.jpg)
![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_108_h_108_q_80/picture/look/s_look-61793.jpg)
![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/-/20250725165932/img/default_img/region_squ_320_001.jpg)












