参議院選挙があす20日、投開票となる。「現金給付か、減税か」を争点として掲げられ、事前の情勢に関する報道では、「日本人ファースト」を掲げる参政党が支持を拡大していることが伝えられる。
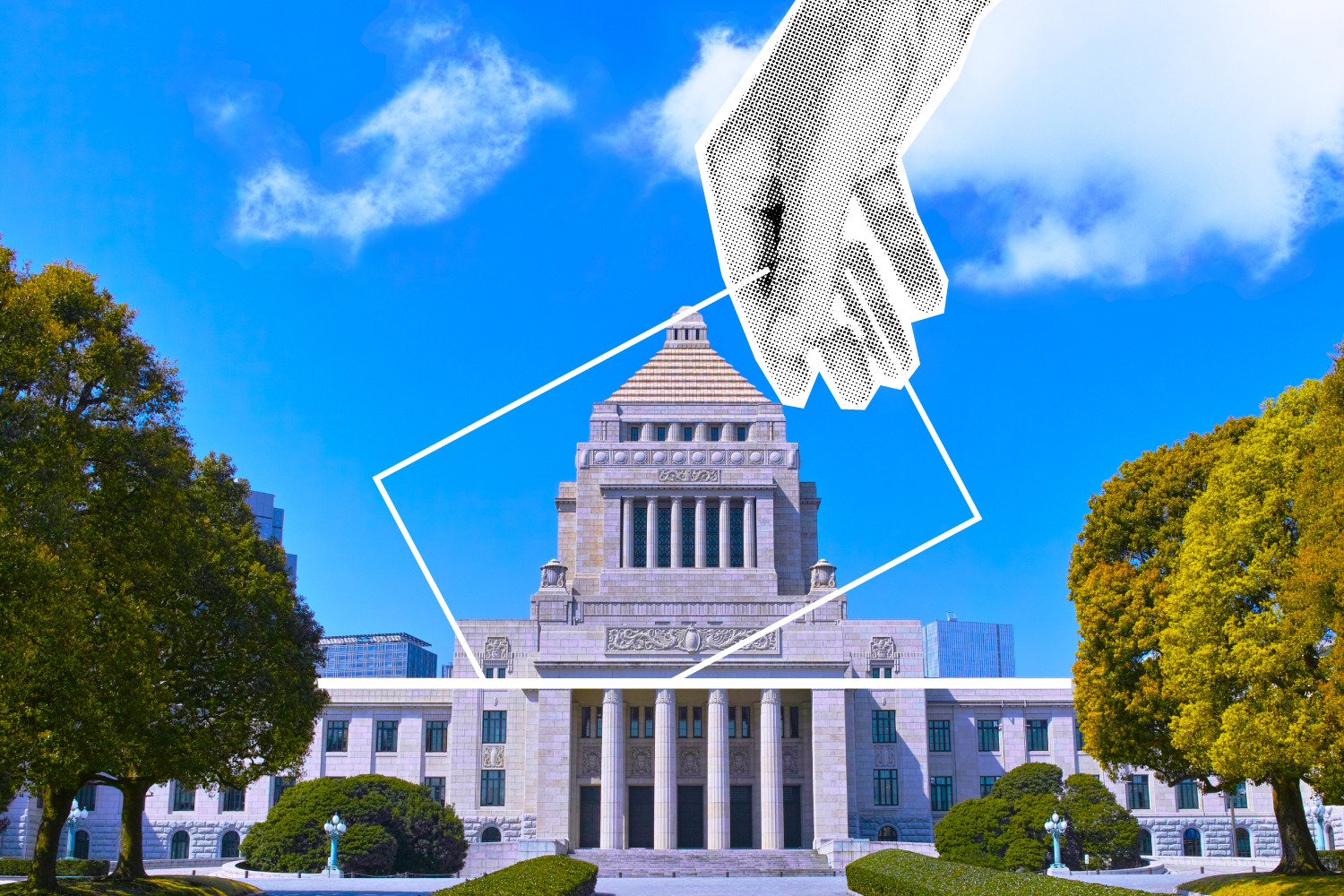 (Ekaterina Dukhanina/7maru/gettyimages)
(Ekaterina Dukhanina/7maru/gettyimages)それに伴い外国人労働者問題が争点として注目されつつある。また、SNSの浸透により、各政党が掲げる政策の真偽や正当性も議論されている。
石破茂首相は勝敗ラインを、非改選議席を含めて自民、公明両党で過半数維持としており、選挙結果が今後の政権運営を左右することにもなる。
私たちは何を見て、誰に投票すれば良いのか。選択への視点を与える記事を紹介する。
<目次>
消費者の「食の不安」を政治利用する参政党、れいわ…野党の政策が非科学的であるこれだけの理由!与党が今、すべきこととは?
〈欧州債務危機が与える教訓〉参院選・与党過半数割れで起こりうる日本経済への影響とは?
外国人労働者へ本当に“優しい”政党はどこだ?あえて言おう、「多文化共生社会」の危うさ
年金制度改革で「得する」世代と「損する」世代の境界はどこか?参院選で見るべき視点
「減税ポピュリズム」はいらない!高橋是清から現代の日本人が学ぶべきこと
消費者の「食の不安」を政治利用する参政党、れいわ…野党の政策が非科学的であるこれだけの理由!与党が今、すべきこととは?
 参院選の各党の公約を見ると、科学コミュニケーションに反したものばかりだ(代表撮影/ロイター/アフロ)
参院選の各党の公約を見ると、科学コミュニケーションに反したものばかりだ(代表撮影/ロイター/アフロ)日本の食品安全は世界最高水準の科学的基盤を有しているにもかかわらず、消費者の不安は大きい。参院選向けに発表された各政党の政策を見ると、一部の政党がこの「不安のギャップ」を政治的に利用し、科学的に根拠のない政策を提案している実態が見えてくる。これらの政策は、科学に対する国民の信頼を損ない、真の公衆衛生と科学的リテラシーの向上に逆行するものである。
れいわ新選組は、マニフェストにおいて「農薬・添加物の規制強化」を掲げている。
この政策は、現行の規制が不十分であるという誤った前提に基づいている。現在の規制は2003年に制定された食品安全基本法に基づいている。その核心は、科学的独立性と客観性を確保するために、「リスク評価」と「リスク管理」の分離原則を導入した点にある……
続きを読む⇒消費者の「食の不安」を政治利用する参政党、れいわ…野党の政策が非科学的であるこれだけの理由!与党が今、すべきこととは?
〈欧州債務危機が与える教訓〉参院選・与党過半数割れで起こりうる日本経済への影響とは?
 参院選の結果は、その後の経済政策へ大きな影響を及ぼし得る(アフロ)
参院選の結果は、その後の経済政策へ大きな影響を及ぼし得る(アフロ)7月20日に投開票となる参議院選挙を前に様々な世論調査が出始めている。注目点は言うまでもなく、「自民・公明の連立与党が非改選議席と合わせて過半数(50)の議席を確保できるかどうか」に集中する。この点、「過半数確保は難しい」との報道も多く、6月の都議会議員選挙で歴史的大敗を喫した経緯を踏まえれば、その観測に違和感は小さい。衆院に続いて参院でも与党過半数割れとなると、政権交代の可能性すら頭を過ぎる事態である。
より具体的な想定をすれば、与党が過半数割れとなり、石破茂政権が総辞職に至り、その上で野党連携の上で(野党のいずれかから)首班指名を行うことができれば政権交代が実現するものの、今の野党を見渡す限りそこまでの団結にはなるまい。そうなると少数連立与党となった自公はいずれかの野党を連立政権に取り込む流れになるが、現実的には立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の3択である。
どの選択肢になるのかは石破首相を筆頭とする自民党執行部が敗戦の責任をどういった形で処理するのかに依存するはずで、全く予想がつかない(例えば石破首相と玉木・国民民主党党首は非常に折り合いが悪いと目され、総辞職がなければ国民民主党との連携は考えにくい、など)。この辺りは政局に詳しい専門家の議論に委ねたい……
続きを読む⇒〈欧州債務危機が与える教訓〉参院選・与党過半数割れで起こりうる日本経済への影響とは?
外国人労働者へ本当に“優しい”政党はどこだ?あえて言おう、「多文化共生社会」の危うさ
 (koumaru/gettyimages)
(koumaru/gettyimages)参院選の焦点といってもあまりにも政党が多くてどう整理したら良いのかが難しい。そこで、ここでは、選挙戦で急浮上した外国人労働者問題についての各党の政策について考えてみたい。以下、「 」でくくってある部分も、正確な引用ではなく、要約であると断っておく。
自民党の外国人労働政策は、具体的には、運転免許切り替え手続きや不動産所有などの問題を、法令に基づき厳格・毅然と対応し、「違法外国人ゼロを目指す」である。これは奇妙な政策スローガンである。
野党がこう主張するなら分かるが、自民党は与党で政府と一体なのだから、違法なことを許してはいけない。違法を取り締まることができていないのは、自分たちの行政執行能力が低いと言っているに等しい……
続きを読む⇒外国人労働者へ本当に“優しい”政党はどこだ?あえて言おう、「多文化共生社会」の危うさ
年金制度改革で「得する」世代と「損する」世代の境界はどこか?参院選で見るべき視点
 (years/gettyimages)
(years/gettyimages)基礎年金を底上げする措置などを盛り込んだ年金制度改革の関連法が6月13日に参議院本会議で自民、公明と立憲民主党などの賛成多数で可決・成立した。ただし、底上げ措置を講じた場合、将来的に年間2兆円ほど追加で必要となることが見込まれている。国庫負担の財源確保が課題となっており、4年後の公的年金の財政検証で将来的に基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合などに、厚生年金の積立金を活用して、底上げ措置を講じるとした。
20日に投開票が行われる参議院議員選挙では、既に限界に達している社会保障改革を争点とすべきである。以下に示す試算も念頭に投票に行っていただければ幸いである。
基礎年金底上げとは、財源が厳しい基礎年金を比較的安定している厚生年金の積立金によって引き上げようとするものである。厚生年金の報酬比例部分において、本来であれば年金額の伸びを物価や賃金の伸び率に比べて低くおさえるマクロ経済スライドが2026年度に終了予定であったが、36年度まで適用延長することで厚生年金を減額して基礎年金の増額に振り替える。また、厚生年金の積立金を基礎年金給付財源として流用する財政措置を行うことで、基礎年金のマクロ経済スライドの適用期間を短縮するものである……
続きを読む⇒年金制度改革で「得する」世代と「損する」世代の境界はどこか?参院選で見るべき視点
「減税ポピュリズム」はいらない!高橋是清から現代の日本人が学ぶべきこと
 1896年建設の日銀本館。高橋是清はペルーで銀山投資の失敗後、日銀建築事務主任として建設に携わった(BLOOMBERG/GETTYIMAGES)
1896年建設の日銀本館。高橋是清はペルーで銀山投資の失敗後、日銀建築事務主任として建設に携わった(BLOOMBERG/GETTYIMAGES)「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」は、米国の作家マーク・トウェインの格言だ。技術革新や人権の伸長など、社会環境が昔と異なる現代に同じことは起きないだろうが、それでも似たようなパターンや流れは再び現れるという意味だ。
19世紀後半から20世紀初頭にかけて、蒸気機関による交通革命や電信による通信革命、メディアの発達などにより第一次グローバリゼーションが起こると、リカードの比較優位の理論(各国は他国と比べて「より効率的に生産できるもの」に特化して貿易を行うことで、全体の生産性が向上し、すべての国が利益を得られる)のとおり、貿易が盛んになり世界経済は繁栄した。だが、その一方で先進国の内部ではグローバリゼーションによって富を享受する者と、労働集約的な職業では取り残される者に分かれて深刻な経済格差が発生した。これが1914年から始まった第一次世界大戦の開戦原因になったとの分析もある。
現代は冷戦終了後の安価になった航空料金、コンテナによる物流革命、インターネットの普及などによって貿易が盛んになり、第二次グローバリゼーションの時代とも呼ばれてきた。まさに歴史は韻を踏んでいるわけだが、そうした中で第一次と同様に先進国内では経済格差が生まれ、そうした不満が欧州における右傾化を促し、米国ではトランプ大統領を生み出したとも言える……
続きを読む⇒減税ポピュリズム」はいらない!高橋是清から現代の日本人が学ぶべきこと





































































![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_108_h_108_q_80/picture/look/s_look-61790.jpg)
![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_108_h_108_q_80/picture/look/s_look-61793.jpg)
![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/-/20250725165932/img/default_img/region_squ_320_001.jpg)















